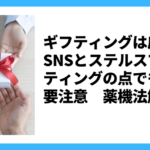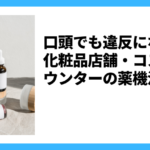新着記事
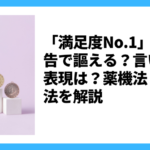
「満足度No.1」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法・景表法を解説
商品の広告で「満足度No.1」という表現は、聞いた事がありますよね。 「顧客満足度」「業界満足度」など表現は色々ありますが、この表現はそもそも薬機法と景表法に違反する可能性があり、合理的な根拠に基づいたものでなければいけ […]
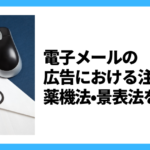
電子メールの広告における注意点 薬機法•景表法を解説
広告宣伝のために電子メール広告や、メルマガ送付することでユーザーに商品やサービスの宣伝が行われることがあります。メルマガの送付にも法的な規制があります。特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)、特定 […]
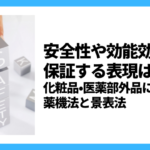
安全性や効能効果を保証する表現はNG?化粧品•医薬部外品に関する薬機法と景表法
商品の広告として、「安心安全」「効果を保証」など、安全性を強調するものや、成分の効果について保証する表現は説得力のある言葉に聞こえますが、広告表現としては認められません。 この表現が薬機法や景表法で違反する理由や適切な広 […]
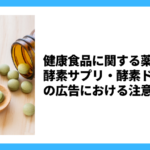
健康食品に関する薬機法 酵素サプリ・酵素ドリンクの広告における注意点
酵素には消化や代謝などを助ける働きがあると言われ、酵素を含むサプリやドリンクなどは健康食品として人気があります。 しかし広告などで酵素を扱う場合には法律に抵触しないように十分注意すべきと言えます。広告で表現する内容によっ […]
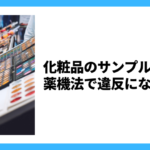
化粧品のサンプル配布は薬機法で違反になる?
今回は、化粧品をサンプル・プレゼントとして配布する場合の規制について解説していきます。 薬機法とは 「薬機法」とは正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で「医薬品医療機器等法」と略され […]

インフルエンサーコスメも薬機法の対象?YouTubeやSNSに注意
SNSの普及により、インフルエンサーという言葉を耳にする機会が増えたのではないでしょうか。インフルエンサーとは、influence(影響・効果)という英語が語源で、世間や人の思考や行動に大きな影力のある人物のことをいいま […]
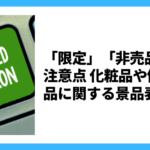
「限定」「非売品」の注意点 化粧品や健康食品に関する景品表示法
期間限定キャンペーンでは、お得さを伝えるための「二重価格表示」が認められていますが、ルールが多いので気をつけなければいけません。景品については、商品・サービスにつけられる限度額が決まっているので注意が必要です。 この記事 […]

健康食品会社の社員がSNS・YouTubeで情報発信するときの注意点
SNSやYouTubeはインフルエンサーの商品レビューの場とされていましたが、最近では健康食品会社の社員が自社や他社の製品の情報発信する機会も多くなっています。 ただ、会社の知らないところで社員が法律やガイドラインに違反 […]